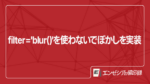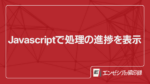【OER3000プラグインを作る②】作業前の下準備
フリーウェアの3D鉄道シミュレーター「RailsimⅡ」のプラグインの制作過程を記録に残そうというシリーズ。
すみませんがまだ3Dモデリングには入らず準備編となります。

テキストファイルで情報管理
寸法のメモやマテリアル管理など、制作に必要な情報の管理のために、テキストファイルを作る。手書きのメモがいいという方はそれでも良い。私も手書きとデジタルを併用していたが、マテリアル管理などは頻繁に書き換えするのでデジタルの方が良い。
前回の70系制作時のファイル内容は以下の通り。
■TODO
↑あとでやっておくこと、作業再開したときにやることをメモ。思い出すために
■寸法メモ
↑分かっている寸法を全てメモする
■Blenderオブジェクト番号メモ
↑Blenderでのオブジェクト名の付け方(大まかな部品グループ、先頭中間どっち用、スムージングの角度など分かるようにする)
■MetasequoiaXファイル出力メモ
↑出力予定の.xファイル(Railsim用のモデルファイル)を全て羅列
■70系差異一覧(外装)
■70系差異一覧(内装)
↑把握している差異を全て羅列
■Metasequoiaマテリアルリスト
↑.xファイルごとに、何番が何のマテリアルなのかをリストにする。(Railsimではマテリアルを番号で指定しないといけないのでほぼ必須)
また、transparent/NoCastshadowを設定するのか、自己発光するのか、ShiftTextureするのか、するなら移動UV値なども全てメモする
■RailsimPI化メモ
↑プラグインIDを分けるか、スイッチの構成をどうするかなど
■Blender操作覚え書き
■PBRマテリアルのメモ
■Emissive構文の一掃取り換えメモ
■BlenderOBJ出力メモ
↑忘れやすい操作のやり方メモ
バリ展を考える
上記の「■RailsimPI化メモ」に関連して。作業に入る前に、どこまでのバリエーションを再現するのか、大まかでいいので見積もっておく。例えば70系では編成別に①試作車②前期型③後期型、時期別に①リニューアル前②リニューアル後(緑)③リニューアル後(ピンク) のバリエーションがあり、塗装をはじめあちこちに差異がある。手元のメモを振り返ると、とりあえず②前期型②リニューアル後(緑)の形態のみに絞って制作して先行公開しようとしていたようだ。実際は全部いっぺんに作ってしまったが…
バリエーション展開、いわゆるバリ展を前もって考えないと、オブジェクト割りやテクスチャ配分が行き当たりばったりになってしまう。また単純に、作業量がどのくらいか想像するためにも、全体像を把握することは大事である。
さて3000形でもバリエーションを考えていく。3000形は2001年から2019年にかけて第10次まで増備された形式であり、製造次による形態差が多いことで有名である。さらにリニューアルも現在進行しており、調べれば調べるほど沼にハマっていく。
とりあえず「製造次別」として以下のように分類した。
A 1次車
B 2次車(東急)
C 2次車(川崎)
D 3次車
E 4次車
F 5,6次車
G 7次車
H 8次車
J 9次車(中間新造)
K 10次車(中間新造)
5,6次車は調べた限り特に差分がないようなのでまとめた。逆に言えば、それ以外は何かしらの見た目の違いがあるということだ。
そして「時期別」に以下のように分類した。
1 太帯(2004年3月以前の1,2次車)
2 細帯化(2004年3月以降の1,2次車、3次車以降)
3 ブランドマーク掲出(2008年3月~)
4 方向幕書体変更(2018年2月頃~)
5 リニューアル(2022年~)
この分類は私が勝手に行ったもので唯一の正解というのはない。この分類のねらいとしては、プラグインのスイッチで「製造次別」と「時期別」を選ぶだけである程度正しい形態が再現できること。逆に言えば、意図せずありえない形態を出してしまう、みたいなことがなくて済むこと。
例えば「D 3次車」「2 細帯化」を選べば自然にスカートがデカいやつになり、方向幕は3色LED明朝体で、電連は一段になり、6両と8両しか選べなくなる。
これを「スカート形状」「方向幕カラー」「方向幕書体」「電連」みたいにひとつずつスイッチ分けすることもできるが、使う方からしたら面倒だしよく分からなくなる。
使いやすいように、編成を選ぶとその編成の形態がまとめて再現できるようにしている作者さんが多いように思う。
ただ時期別分類については、3000形はこの分類に収まらない差分が多くてどうしてもスイッチが増えてしまう。たとえばインペリアルブルーへの帯色変更は2015年頃から始まり2025年でもまだ終わっていないし、方向幕のフルカラー化もかなりゆっくり進行しているようである。そういった長い期間かけての仕様変更は時期別スイッチに収めることができず単独スイッチになってしまう。
また、一時期だけや一編成だけの特別仕様(防音カバーやラッピングなど)は上記分類には収録せず「特殊バリエーション」として扱った。
特定の姿を再現したいなら編成テンプレートで解決するのも手。
とにかく3000形はバリエーションが多すぎる。新たな形態差が見つかれば、分類の見直しもある。
準備編はこれで終わりです。次回から3Dモデリングに入ります。
まずは、近年登場した3~5次車のリニューアル車から制作していきます。
カテゴリ:雑記